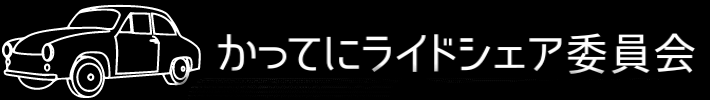2024年4月から日本型ライドシェアがスタートしました。日本型ライドシェアは、国内のタクシー需要の増加やタクシードライバー不足によって、タクシーの供給が不足している課題を解決するための施策です。そのため、ライドシェアサービスはタクシー事業者が運行の管理を行っております。一方で世界のライドシェアの仕組みとのギャップがある状態です。
本記事ではライドシェアの意味や歴史を振り返るとともに、世界中でサービス展開されているライドシェアの種類やメリット・デメリットを整理しました。また日本型ライドシェアの概要と利用方法についてもご紹介します。
ライドシェアとは
ライドシェア(ライドシェアリング)は自動車のシェアリング方法の1つです。ライドシェアは文字通り、Ride(乗る)をShare(共有)することを意味します。いわば「相乗り」と同じ意味です。一般的に「相乗り」というと、タクシーを利用する際に行き先が近い客同士がタクシーをシェアすることを思い浮かべると思いますが、最近流行りのライドシェアは、タクシーだけではなく一般の個人ドライバーとドライブをシェアすることも「相乗り」といいます。
相乗りは、より多くの人が1台の車両を使用することで、燃料費、高速料金、運転のストレスなど、各人の移動コストを削減します。相乗りは、移動を共有することで大気汚染、二酸化炭素排出量、道路の渋滞、駐車スペースの必要性が軽減されるため、より環境に優しく持続可能な旅行方法でもあります。特に大気汚染が深刻な時期や燃料価格が高騰している時期には、相乗りを意識した論調になることがあります。
また、他の自動車シェアリング方法にカーシェアがあります。カーシェアは事業者・個人が所有する車両を利用者(ドライバー)に貸し出すサービスです。
ライドシェアの種類
ライドシェアは大きく2つに分類できます。ひとつはTNC(Transportation Network Company)サービス型ライドシェア。もうひとつはカープール型ライドシェアです。
TNCサービス型ライドシェア
「Uber」や「Lyft」などがTNCサービス型ライドシェアの代表です。モバイルアプリやウェブプラットフォームを通じて、ドライバーと乗客を繋げるサービスを提供しています。
これにより、利用者はスマートフォンなどのデバイスを使って自分の位置情報を登録し、近くのドライバーを呼び出すことができるため、通常のタクシーよりも手軽に車を手配できます。また、プラットフォーム内で行先を指定することによって料金の支払いを事前に完了することができます。そのためタクシー料金の時間制運賃のような費用が発生せず、割安になる場合もあります。これらのことからTNCサービス型はタクシーやレンタカーと競合しがちです。 ドライバーは、運転資格保有者のタクシードライバーと異なり一般ドライバーの方が登録可能です。日本でいう二種免許を保有していなくても登録することができるので、隙間時間に副業や兼業としての働き方も可能です。ただし誰でも登録できるわけではありません。安全性を担保するために、運転免許の登録や車両保険取得、定期的な車両点検など一定の要件を満たしている必要があります。海外では過去の犯罪歴なども項目に含まれる場合もあります。
Uber等のTNCサービス側は、利用者とドライバーのマッチング率を最大化させることで高い収益を得ることができるビジネスモデルになります。このビジネスモデルを維持するため、ドライバーと利用者の双方がお互いを評価することでマッチングの障壁を緩和するなどの工夫をプラットフォーム内で行っています。高評価してもらうためには、乗客・ドライバーはそれぞれマナーを守ってサービスを利用することが重要です。
ドライバーにとっても利用者にとってもメリットを受けられそうなTNCサービス型ライドシェアは便利さと経済性を提供する一方で、利用者の安全やドライバーの労働条件などの問題についても注目されています。日本など国や地域によっては、利用禁止・限定がされている場合があるため、世界的に安全に利用するためには課題が残っている状況です。
カープール型ライドシェア
カープール型ライドシェアは、一般ドライバーが自家用車に出発地や目的地が同一である者を同乗させるライドシェアです。ヒッチハイクのようなイメージがわかりやすいと思います。近年はスマートフォンでその場で直前に申込むことも可能です。料金形態についてですが、日本の場合ドライバーはサービス料金を利用者に請求すると法律違反となります。ガソリン代等の実費程度まで受け取れるが、利益を得ることはできません。カープール型にも、バンに大人数が相乗りするバンプール型や、通勤途中のドライバーが乗り場に向かい利用者を相乗りさせて目的地まで届けるカジュアルカープール型などがあります。
カープール型ライドシェアは、利用者にとっては必要最低限のコストで目的地に移動することができるメリットがありますが、サービスを提供する企業側は法的な制限によってサービス料を受けることができないためサービスを拡張させ利用者への新しい付加価値を提供することが難しいという課題があります。 そのため、ライドシェア市場の拡大はカープール型ライドシェアよりもTNCサービス型ライドシェアが中心になると想定されます。
ライドシェアのメリット
利用者側のライドシェアメリット
ライドシェア一番のメリットはコスト面だと考えます。1台の車を他のライダーとシェアして乗りますので、コストが安く済みます。例えば2人でシェアすればタクシーをシェアする場合には半分の料金で済みますし、3人なら3分の1で済むことになります。また、配車時に事前決裁することが可能なので明朗会計です。タクシーの時間制運賃(時間拘束の割合が高い運送時に適用され、タクシー到着から運送終了までにかかった時間で算出)のような料金が追加で発生することはありません。
もう一つメリットとして考えられるのは、ライドシェアを通じてコミュニティができることです。同じ方向に行く人同士がつながることで、会話を楽しんだり、新しい友人を作ったりすることができます。
ドライバー側のライドシェアメリット
ドライバー側のメリットは、隙間時間を活用して副業ができる点です。特に車の利用が少なく副業できる時間がある人にとって経済的メリットにつながります。ドライバーは自分の車を効率的に活用でき、同時に利用者は公共交通機関よりも快適な移動をすることができるでしょう。
ライドシェアのデメリット
- 柔軟性
ライドシェアは、ルートの停車や勤務時間/パターンの変更に対応するのに十分な柔軟性を持たせるのが難しい場合があります。これがライドシェアをしない一番の理由であるという調査結果もあります。サービス側がドライバーの最小限の遅延や単一の降車/乗車場所を保証するケースは現時点で在りませんでした。
- 信頼性
ライドシェアサービス利用者は、必ずしも合意された乗車を行うとは限りません(未決済の場合)。ドライバーは乗車指定場所に向かっても利用者が見つからない状況になると移動コスト・時間的コストで損をすることになります。ドライバー視点では利用者の信頼性を見極めるのが重要です。一方でドライバーの運転の質や対応に問題があるケースも事例として存在します。利用者はライドシェアサービス自体に不信感を持つ体験をすることになります。利用者視点ではドライバーの信頼性を見極めるのが重要です。
- シームレスな利用
ライドシェアサービスは国によって法律で厳しく取り締まっています。そのため、自国で利用できたサービスが旅行先の国で利用できない場合があります。
世界の主なライドシェアサービス
今後世界中でさらにライドシェアリングサービス(TNCサービス型)の普及が見込まれると予想されています。そのためサービスを提供している企業も世界中に存在します。以下に代表的なサービスを紹介します。
- Uber Technologies Inc.(アメリカ)
- DiDi Global Inc.(中国)
- Gett(イギリス)
- Grab(シンガポール)
- Bolt Technology(エストニア)
- Careem(アラブ首長国連邦) 2012年設立 ※2019年3月Uberが買収
- Cabify(スペイン)
- Lyft(アメリカ)
- Car2go(ドイツ)
ライドシェアによる社会問題
2016年に衆議院が掲載している質問本文情報から、自家用車ライドシェアに関する犯罪や違法行為の報道が多数あり社会問題になっていることがわかります。詳細はこちらをご覧ください。
日本型ライドシェアとは
2023年12⽉20⽇に第3回デジタル⾏財政改⾰会議が実施されました。交通分野の成果の一つに、タクシー・ドライバーの確保のための規制緩和、地域の⾃家⽤⾞・ドライバー活⽤によるライドシェア(タクシー事業者の運⾏管理下での新たな仕組みの創設)、⾃家⽤有償旅客運送制度の改善、タクシー事業者以外の者が⾏うライドシェア事業に係る法律制度についての方針が決まりました。
対策方針
- タクシー・ドライバー確保のための規制緩和(二種免許有無の緩和、地理試験の廃⽌など)
- 供給を補うため地域の⾃家⽤⾞や⼀般ドライバーを活かしたライドシェアサービスを2024年4⽉から開始予定。タクシー事業者の運⾏管理の下で仕組化
- ⾃家⽤有償旅客運送制度を2023年内から改善
- タクシー事業者以外の者がライドシェア事業を⾏うことを位置付ける法律制度について、2024年6⽉に向けて議論
- 供給量増加に向けて、自動運転技術の活用を検討。⾃動運転レベル4の社会実装・事業化に必要な初期投資⽀援の予算措置を開始
- ⾃動⾛⾏⾞両のルールの在り⽅を検討する場を2023年12⽉に設置
- ⾃動運転の⾛⾏に係る審査に必要な⼿続きの透明性・公平性の確保策を検討するための関係省庁の枠組みを構築
そして、2024年4月8日より東京都で日本型ライドシェアの運行が開始されています。
<関連記事>
ライドシェアと個人タクシーの違いは?
一見ライドシェアと個人タクシーは同じように思うかもしれません。しかし、日本においてはドライバーの特徴や資格、雇用形態など異なる点があります。また乗車方法にも特徴があります。
| ライドシェア | 個人タクシー | |
| ドライバーの雇用形態 | パート | 業務委託(個人事業) |
| ドライバーの資格 | 第一種運転免許 | 第二種運転免許 |
| 運行時間 | 限定(タクシー不足の時間帯) | いつでも |
| 乗車方法 | 配車予約アプリのみ | 流し含めた全てに対応 |
日本型ライドシェアの利用方法について
ライドシェア今後の展望
これまでライドシェアについてまとめてきました。ライドシェアは今後大きく発展する可能性のある市場です。具体的にどのような発展の可能性があるのか、最後に所感をまとめます。
ライドシェア市場がさらに発展するためにはいくつかの課題解決が求められると考えます。法整備の観点ではもちろんですが、課題を解決してライドシェアサービスそのものの付加価値向上も必要になります。個人的に注目しているのは次の2点です。
完全自動運転×ライドシェア
自動運転との組み合わせは非常に期待されている領域だと考えます。ライドシェアの課題の一つとして「安全性」の担保があげられます。「安全性」にもいくつか要素があり、事故を起こさない運転技術の担保もあれば、ドライバーの人格的な安全性の担保も含まれていると考えます。
自動運転技術によって将来ドライバー不在で目的地まで移動する世界が訪れる可能性があります。この世界までたどり着くことができれば、自動運転によって安全性の担保ができると考えます。
ライドシェアのもう一つの課題として「乗客に必要なタイミングでのサービス提供」があります。完全自動運転によってドライバーが不要になるため、配車数の増加が見込めます。さらにAIも活用することで乗客ニーズを予測した車両の配置・待機も可能になり乗客は待ち時間を最小限にサービスを利用することができると考えます。
マルチモーダル×ライドシェア
少し違った着眼点になりますが、ライドシェアに特化したマルチモーダルも面白い取組ができるのではと個人的に考えます。先に述べた通り、ライドシェアのサービスは世界中に多く存在し、ライドシェアのサービスも大きくTNCサービス型とカープール型と分岐します。移動の選択肢が非常に多いため、利用者は適切なタイミングで最適なサービスを気軽に選択することができません。そこでライドシェアに特化したマルチモーダルサービスで利用者に選択肢を提示することができれば、コスパ・タイパを最適化したサービスの選択が可能になると考えます。利用者は配車の待ち時間を最短にしたい、できるだけコスパ抑えて移動したい、など様々なニーズがある中でそれらに応える一手として検討の余地はあるのではと考えます。
まとめ
いかがでしたか?ライドシェアに関する情報の参考になれば幸いです。