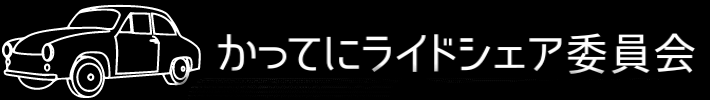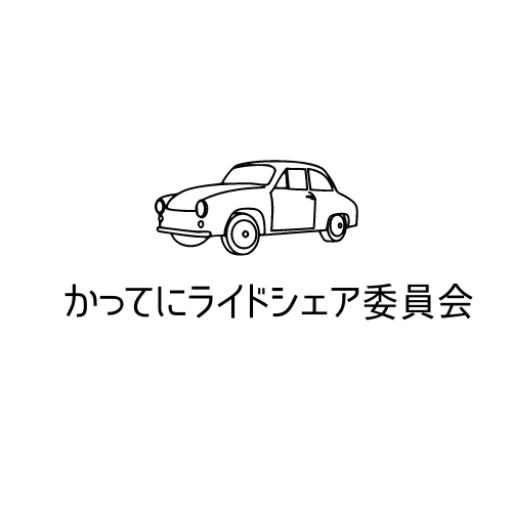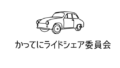2023年12月に決定された「デジタル行財政改革会議の中間とりまとめ」において、タクシー事業者が運送主体となって地域の自家用車・ドライバーを活用し、タクシーが不足する分の運送サービスを供給すること(日本型ライドシェア)が決定され、2024年4月から東京、愛知、神奈川、京都の一部エリアから解禁となります。
今後は、タクシーが不足する地域・時期・時間帯におけるタクシー不足状態を、道路運送法第78条第3号の「公共の福祉のためやむを得ない場合」であるとして、日本型ライドシェアのサービス提供を可能とする予定です。
2024年3月13日と3月29日に国土交通省から発表があり、東京や大阪、京都など主要都市のタクシー不足調査を行った後、タクシー事業者がライドシェアの実施意向があれば、4月意向順次サービス開始となる見通しです。
では、調査エリア以外のライドシェア実施はどうなるのでしょうか。こちらについても3月29日に国土交通省から発表がありましたので、この記事ではその内容をお伝えいたします。
調査エリア以外のライドシェア実施について
国土交通省の発表によると、政府の調査対象外エリアのライドシェアについては「簡便な方法により不足車両数を算出し、タクシー事業者に実施意向がある場合は、4月以降順次開始して良い」と記されています。簡易な算出方法とは、「金曜日・土曜日の 16 時台から翌 5時台をタクシーが不足する曜日及び時間帯とし、当該営業区域 内のタクシー車両数の5%を不足車両数とみなす」とのことです。
上記に限らず、営業区域内の自治体が、特定の曜日及び時間帯における不足車両数を運輸支局へ申し出た場合は、その内容を不足車両数とみなし、タクシー不足分を補うライドシェアの運行本数が決まるようです。ただし地域によっては適用外となる場合もあるので注意が必要です。
運輸局への申請については国土交通省のホームページに申請書が公開されました。必要事項を記入のうえ受理された場合に、該当エリアでのライドシェア運行が許可されます。なお、申請手続きは「ライドシェア事業を実施しようとする法人タクシー事業者が行う」とされています。
現時点でライドシェア事業を運行するためには、自治体の調査とタクシー事業者の協力が必要になります。詳しくはこちらをご覧ください。
まとめ
国土交通省が推進し、各自治体のライドシェア実施に向けてのルールが整ってきました。自治体・タクシー事業者・住民が三位一体となれば、実現が加速するかもしれません。
最後まで読んでいただきありがとうございました。他の記事もぜひご覧ください!